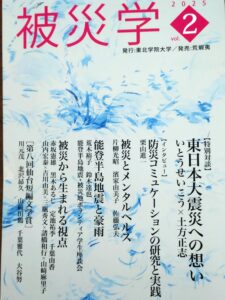第8回仙台短編文学賞授賞式、『被災学』第2号の刊行
仙台は桜の花が満開となり、絶好の花見日和である。台原森林公園に隣接した仙台文学館において開催された第8回仙台短編文学賞授賞式、祝賀パーティーに出席し、東北学院大学賞のプレゼンテーターとして講評をしてきた。
(広くてモダンな仙台文学館。仙台文学館の初代館長は井上ひさしであり、仙台市出身の作家にちなむ展示が催されている)
東日本大震災を契機に始まった仙台短編文学賞も今年で8回を数え、15歳から91歳までの作者から応募作品318編を集めた。選考委員は、仙台出身の映画監督・脚本家・小説家の岩井俊二さんが担当した。大賞、仙台市長賞、河北新報社賞、プレスアート賞の発表に続いて、大学生・高校生部門に相当する東北学院大学賞が発表されたが、北沢昴久さんの「こだまのいう通り」が選ばれた。
(第8回仙台短編文学賞の受賞者前列とプレゼンター後列。中央が大賞の作者安堂玲さん。その左後ろは選考委員の岩井さん。安堂さんの受賞作品「相沢のおとうさん」は仙台の老舗眼鏡店(株)「メガネの相沢」にまつわる物語で、同社の相澤久美子社長も駆けつけ、祝賀パーティで挨拶した)
北沢さん受賞作品はその構想力において秀逸である。すなわち、羽で動く空の上の世界と足で動く人々の世界を並行させ、主人公が空の上からケヤキの葉の色を塗る仕事をしながら、地上の人々に愛着をもって眺めるという設定である。主人公の仕事が忙しくなる「卯月」、黄色の色を塗る仕事が始まる「神無月」と和風月名を使いながら、空の上の世界を絶妙に描き、地上の人々の世界の「12月」、定禅寺通りの光のページェントで終わる場面の転換は見事としか表現の仕様がない。
(北沢昴久さんとともに。北沢さんは、執筆当時東北大学理学部の4年生。新潟県出身であるが、「杜の都」仙台に対する愛着をこの作品に凝縮させた)
受賞作品は、本学が刊行している『被災学』第2号に掲載されている。同誌には、東北学院大学が加盟している私立大学連盟主催の「私大連フォーラム2024 これからの時代に向けた私立大学の未来型防災教育を考える」における特別対談が冒頭に掲載されている。「東日本大震災への想い」と題されたこの対談では、作家のいとうせいこうさん(早稲田大学法学部卒)と、仙台短編文学賞の実行委員で有限会社荒蝦夷代表の土方正志さん(本学文学部卒)によってなされ、被災・防災において地域の拠点としての私立大学が果たすべき役割も論じられている。東北学院大学は、被災地にある大学としての役割を今後とも果たしていきたい。
(『被災学』第2号。東北学院大学発行、荒蝦夷発売、税込定価2750円、Amazon、一般書店でも購入できる)